鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室
【ファシリ】10/15ファシリテーションWG委員、地域包括ケア専門職“絆”③で活動!
地域包括ケア専門職“絆”研修~仲間同士、知る・つながる・高め合う~3回シリーズの3回目が10月15日に開催されました。
( “ 絆 ” 研修の概要 )
地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係の多職種(専門職)を対象に、事例を通し①退院支援「病院から在宅へ」、②生活支援「在宅療養」、③終末期支援「看取りの時期」での専門職の役割、多職種連携の重要性を学び、実践につなげていくことを目的に3回シリーズで実施します。
今回は③終末期支援「看取りの時期」を開催しました。
■ 日時 平成29年10月15日(日) 13:15~16:25
■ 場所 東部医師会館3階研修室
◎ 研修参加者 70名(内多職種研修WG関係者3名):9グループ
※ 今回は10名のファシリテーターが、9/14、9/28、10/5に事前準備と当日最終打合せ後に研修にのぞみました。


◆ファシリテーター紹介・アイスブレーキング(中瀬香里ファシリテーター:ウエルフェア北園渡辺病院MSW)

◆後半のワーク②のプレゼンテーション(山根綾香ファシリテーター:鳥取市立病院看護師)
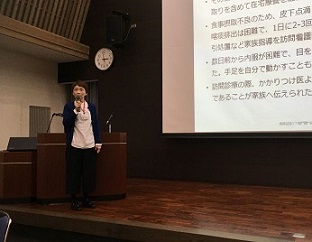
○ ファシリテーターの振り返りと感想
【 反省点 】
- 討論内容と違った意見が出たとき修正に入ったが、グループ内から軌道修正を促すような話がされたので、もう少し経過を見ても良かった。
- ワーク①で情報整理の時間が不足したので、次のワーク②ではタイム管理を提案し実施したが、各自が記録を取っていたため、共有には不十分だった。
- ワーク②の書記は記録用紙がテーブルを回っているだけでなかなか決まらなかった。そのため全体発表への手あげもあいまいだったのでもう少し介入が必要だった。
- ファシリテーターとして発言者のフォローとして意見を述べたかったが、迷ったうえしなかったが、どうしたら良かったのだろう。
【 良かった点 】
- 研修に参加する立場とファシリテーターとして参加する立場ではまた違った見方が出来て勉強になった。
- メンバーにベテランが多い中、若いスタッフが1名おられ発言がなかったので、促して発言していただいた。その後は自発的に意見を出され、一度意見を出すと話しやすくなるなと感じた。
- 最初の「1分程度での発表」のアナウンスは、発表準備に効果があった。
- グループワーク②で発言が全員終り、「どうしましょう」のSOSがあったが、少々のアドバイスとメンバーからの誘導もあり、ワークが深められた。
- 参加者全員の意見交換ができて良かった。
- 役割(司会、書記、発表)が決まれば、全員の意見を司会者が順番に聞き、全員の意見が出た。
- やや距離をおいた状況で介入開始し、グループの様子から、必要最低限の介入で十分と判断した。
- 医療・介護それぞれの立場での意見交換がされ、お互いの認識が広がったワークが出来ていた。
- 気になる場面では出た意見をまとめて、メンバーに投げかけてみるといった意識的な介入をさせてもらった。
- 参加者が専門職としてしっかり向き合い考え、自分にはない視点の意見には受け入れ、理解されようとする姿勢が見られた。
- 症例以外に実際の終末期のご家族との体験談を聞いたことはメンバーの参考になったと思う。
【 今後の提案・工夫 】
- 意見の情報整理・共有がしやすいように、ホワイトボードへの板書、フリップトークといった思考ツールを使用するのも良いと思った。
- ワーク②で4つのキーワードがあり(①本人・②家族・③医療・④介護)、マスを使い4つに区切って記入するようにしたら、情報の整理がし易かったのではないかと考える。
- ファシリがいることを参加者がどうとらえているか、アンケートなどで記載してもらいたい。

【 プレゼンテーターの振り返り 】
当日までのマイクロティーチングが、大変勉強になりました。ファシリテーターの皆さんから、アドバイスをもらう事で自分では気づかなかった点に気づけましたし、普段の自分の癖を振り返る機会にもなりました。
グループワーク後の発表での全体共有で、意見の拾い上げが難しかったです。たくさんの意見を一度に言われると覚えきれず、復唱ができませんでした。振り返りで、「一つか二つに絞って発表をお願いします」と伝える方法を教わり、次の機会に活かしてみたいと思いました。

【 事務局より 】
ファシリテーターとして回を重ねることで、基礎の上に工夫や今後の研修に向けての提案なども振り返りの中で出てくるようになりました。今回は人数が少なめでしたが、研修の進行、グループワークにそれぞれの特徴が発揮されていたと思います。今後は、プレゼンテーターの役割も増えてくると思います。プレゼンのスキルアップを含めたフォローアップの機会を企画したいと考えています。また、今後の研修にもより深く関わっていただき、新しい仲間を育て、仲間同士で地域の“絆”を深めていく力となっていただくことを期待します。