鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室
第40回 東部在宅医療・介護連携研究会(多職種事例検討会)を開催しました
研究会の場を通した医療・介護にまたがる様々な情報の共有、相互の連携を深めることを目的に、多職種事例検討会を開催しています。
■ 「事例を通した医療・介護連携の情報共有・知識向上」
■ 「研究会参加による、医療・介護関係者の顔の見える関係づくり」
◆ 第40回 東部在宅医療・介護連携研究会 事例検討会
◆ 令和7年8月8日 19時~20時30分 ハイブリッド 開催
◆ 演 題: 「看護職が介護休暇利用と家族の看取りを通じて感じたこと」
~退院前カンファレンスの重要性と在宅療養を支える多職種連携について~
◆ 講 師: 田中 利枝 氏(保健師)
せいきょう訪問看護ステーションすずらん 田中世玲奈 氏(看護師)
◆ 情報提供: 介護休暇法の概要
◆ 講 師: 鳥取県社会保険労務士会 安木 淳一 氏(特定社会保険労務士)
◆ 世 話 人: 鳥取生協病院 院長 皆木 眞一 先生
八頭町社会福祉協議会 岸本 剛 氏(介護支援専門員)
【 開会挨拶 】
皆様、こんばんは。大変暑い日が続いておりますが、本日は、第40回を迎えました事例検討会に御参加下さいまして、ありがとうございます。
皆木先生、岸本さんに世話人となっていただき、今日は、ご家族を看取られた経験について田中利枝さんから、また在宅医療を支えた多職種を代表して田中世玲奈さんからお話をいただきます。また特定社会保険労務士の安木さんから介護休暇についての情報提供をいただきます。
ご家族やご自身の病気に向かい合いながら、仕事のことも考えてゆかねばならないということは、多くの方々が経験することであると思います。今日の研究会を、自らの問題として役立てていただければと思います。よろしくお願いいたします。(松浦会長)
【 演題概要 】
「仕事と子育て、そして家族介護のはざまで揺れる専門職」として、保健師が幼い子どもの子育てとともに、父親(肺疾患・在宅看取り)および祖母(認知症・長期入院)の介護を母親とともに担いながら、職場の理解や制度の壁の中で葛藤した実践と、看護学校時代からの友人が訪問看護師として関わったことについて講演。
【 事例提示 】
・父:(主な病歴)慢性閉塞性肺疾患、気腫合併肺線維症
・祖母:(主な病歴)レビー小体型認知症、心不全、糖尿病
・父の強い希望により在宅療養となる。
・退院前、家族には食事面や転倒リスク、また在宅療養が想像できないことなど不安な気持ちがあった。
・転倒リスクや医療処置が必要な状態のままでの退院、入院中の祖母のこともあり、母一人での対応に不安を感じ、自身が介護休業を取得する決断に至る。決断に至るまでには、仕事や同僚への申し訳なさ、収入面のことなど様々な思いがあり、また休業中も継続するかどうかも悩んだ。
・退院前カンファレンスでは、自分の認識と病院側の説明が違っていたこと、また不安に思っていることには触れられず、問題ないとの判断であった。
・退院日の夜、急変。後々振り返ると、起こりうる事態の想定とその対応などへの準備や話し合い、その共有が不十分であったと感じた。
・訪問看護師が退院前カンファレンスで聞いておきたかったことや困ったことについてアンケート集計。一番困るのが医療物品の不足、医師からの指示の不足であった。
・介護休業中は、介護や家事・育児など慌ただしい日々であった。
・看取り後は、皆が協力し出来ることはすべてやり切ったという満足感があった。

【グループディスカッション】
・在宅支援に切り替わる際はたくさんの不安があったと感じた。
・在宅に切り替わったその日から、緊急連絡先が明確になっていることの必要性を感じた。
・入院中は設備や器具が整っていて当たり前になっていて、退院前に説明を聞く際も特に問題ないと言われると思うが、在宅は設備が整っていないため入院中と同じように考えてはいけないことを感じた。
・医療スタッフも在宅支援のイメージをもっと持てたらいいと感じた。
・家族への説明は専門用語を使うと理解しにくいので、ゆっくりわかりやすい説明が必要。
・医療スタッフ側は、患者の家庭環境を把握した上での説明が進んでいくと良いと感じた。
・起こりうるリスクや対処法を細かく説明しておく必要性を感じたが、時間を要してしまうことや、リスクをどの程度予測できるのかが課題。
・退院後に安心して相談できる体制の構築も必要であり、そのためには多職種での理解や情報の共有の必要性を改めて感じた。
・家族側の重圧や精神的な不安の緩和にも目を向けていかないといけないと感じた。
・患者やその家族と、支援者側の信頼関係をしっかり築いていくことが重要だと感じた。
・支援者側は多職種がチームとなって支援していくことが大切だと感じた
・退院前カンファレンスが、事柄の申し送りの形になっていないか、退院前カンファレンスの在り方を考えていく必要性を感じた。
・退院前カンファレンスで、医療機関側と、家族を含む在宅移行後の支援者側とで意見に相違が出た場合は、擦り合わせをしていき双方が納得できる形にできればうれしい。
【介護休業法の概要】
介護を理由とする離職を防止し、仕事と介護の両立を支援するため、また、働き続けられる環境を整えることを目的に制定された介護休業法について、概要や介護休暇との違いについて、また介護を行う労働者が利用できる制度や、令和7年4月1日の改正法により事業主側に義務化された事項についても詳しくご説明いただきました。
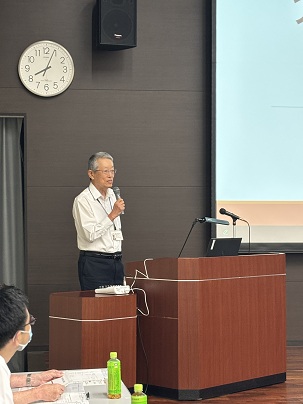
【閉会あいさつ】
病院から在宅への移行に際し、多職種の中で課題をどう引き出し、どう対応していくのか、本日の検討会参加者が前向きに話し合っているのがとても印象的であった。医療機関側として、退院後の経過や、また起こりうることへの予測やその対応について、きちんと伝えておく必要性を改めて感じた。ケースによっては、ケア会議や退院前カンファレンスへの医師の参加や、少なくとも看護師は参加し、ご家族などのニーズに沿った説明の必要性を感じ、自分も学びになった。この度は当事者から事例報告していただき、困ったこと・感じたこと・良かったことなどを共有していただいたことに感謝する。(皆木先生)
当日配布の資料はこちら→ 参考資料2 (PDF) ![]() 参考資料3 (PDF)
参考資料3 (PDF) ![]() 参考資料4 (PDF)
参考資料4 (PDF) ![]()
◆参加者:47名(医師 8名 看護師 9名 介護支援専門員・事務職 各6名、保健師 4名 ソーシャルワーカー 3名 薬剤師・看護教員・介護福祉士 各2名 特定社会保険労務士、認知症地域推進員、鍼灸師、作業療法士、社会福祉士 各1名)