鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室
10/29 地域包括ケア専門職“絆”研修②「在宅療養中(生活支援)」を開催しました
地域包括ケアシステム構築を目指す医療介護福祉関係者を対象に、多職種連携研修会(3回シリーズ)を開催しています。
今回は、第8回目となる地域包括ケア専門職“絆研修”シリーズ②「在宅療養中(生活支援)」を集合形式で開催しました。(東部地区在宅医療介護連携推進協議会:研修支援WG企画)
◆研修のねらい
・地域包括ケアシステムを理解する
・在宅療養を支援するための多職種の役割を理解する
・住民の利益を考えた効果的な多職種連携について学ぶ
◆各シリーズのテーマ
①「病院から在宅へ(退院支援)」
②「在宅療養中(生活支援)」
③「看取りの時期(終末期の支援)」
第8回 “ 絆 ” 研修②「在宅療養中(生活支援)」
■ 日時 令和5年10月29日(日)9時~12時
■ 会場 東部医師会館
■ 研修総括ディレクター
在宅医療介護連携推進協議会副会長 足立 誠司 医師(国民健康保険智頭病院)
< 研修の経過 >
東部地区在宅医療介護連携推進協議会副会長 足立医師から開会挨拶、本研修会の目的の説明があり、研修開始です。

◆ 地域包括ケアシステム・医療介護連携事業について 担当:宮川拓也プレゼンター(鳥取市社会福祉協議会)
地域包括ケアシステム・医療介護連携事業を理解するためのプレゼンテーションが行われました。そのあとは「元気の源」をテーマにアイスブレーキングで緊張を和らげます。


◆ 事例提示・グループワーク① 担当:曽田淳プレゼンター(デイサービスあらいぶ)
生活支援とサービス担当者会議についての説明と、事例をもとにグループワークを行いました。
*サービス担当者会議の開催準備「現状の問題点とその対策」について
グループで意見交換後、会場全体で共有します。生活支援のポイント、サービス担当者会議、地域ケア会議、多職種カンファレンスについてのレクチャーも行われました。
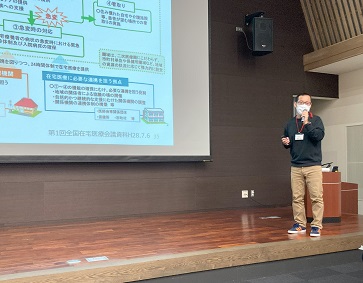
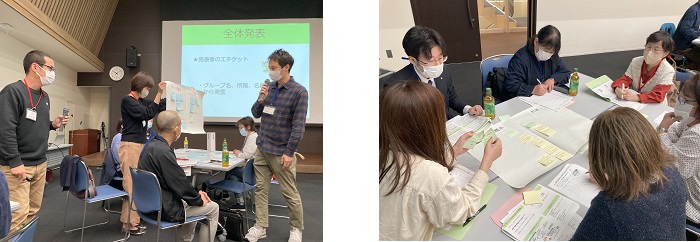
◆ グループワーク② 担当:櫻井重久プレゼンター(鳥取市立病院)
「もしもの時の心構え」について、①将来、事故や病気などで身の周りの事ができなくなり、自分の考えを伝えられなくなった時、あなたならどのようにしてほしいですか? ②大切なご家族がこのようになった場合、どのようにしてあげたいですか?についてグループで意見交換し、会場全体で共有しました。
そして「人生の最終段階における医療について」ガイドラインや国の調査結果の説明や、東部地区の生き方を支援するACPノート「わたしの心づもり」を利用したレクチャーが行われました。
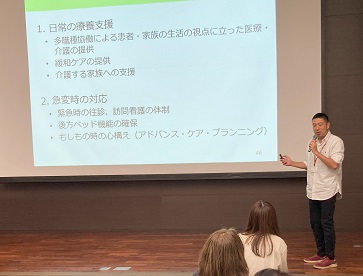

◆ シリーズ②生活支援 まとめ 担当:足立ディレクター
*ケア会議で多職種の役割を理解し、本人の生き方を尊重した合意形成を行うことが大切である
*意思決定を支援し、きちんと引き継ぐことが重要である
*医療・介護だけでなく、人生の視点で本人・家族の希望や幸せに配慮することが大切である
◆ 修了者の紹介と感想
全過程修了者4名の方に感想を述べていただきました。(一部抜粋)
・日々職場では、看護師さんや他の職種の方、皆様にもお世話になっています。今後も頑張って推進に寄与していきたいと思います。
・地域の皆さんがそれぞれの生活を送る上では、皆さんの力が必要です。今後とも支援を頂きたいと思っています。
・1回目は受講生として、2回目からはファシリテーターとして関わらせて頂きました。絆バッジ、とても嬉しいです。
・1回1回新しい発見がありますし、いろんな人の意見を聞いてフレッシュな気持ちになっています。

最後は参加者全員、すてきな笑顔で記念撮影です。今回も大変盛り上がった研修会となりました。

会終了後、プレゼンター、ファシリテーターで振り返りを行いました。

■ グループワーク①②の全体共有 (PDF・77KB)![]() ■ 参加者アンケートまとめ (PDF・206KB)
■ 参加者アンケートまとめ (PDF・206KB)![]()
◎ 研修参加者64名(スタッフ含む)
医師 6名、薬剤師・保健師 各3名、看護師 14名、介護支援専門員・事務職 各10名、社会福祉士 5名、
理学療法士・介護福祉士・地域支え合い推進員・施設管理者 各2名、
作業療法士・MSW・相談員・鍼灸師・心理職 各1名