鳥取県東部医師会 在宅医療介護連携推進室
第28回 東部在宅医療・介護連携研究会(多職種事例検討会)を開催しました
研究会の場を通した医療・介護にまたがる様々な情報の共有、相互の連携を深めることを目的に、多職種事例検討会を開催しています。
■ 「事例を通した医療・介護連携の情報共有・知識向上」
■ 「研究会参加による、医療・介護関係者の顔の見える関係づくり」
◆ 第28回(令和4年8月19日)19時~20時30分
◎ 松浦会長挨拶
皆様こんばんは。本日はご多忙の中、また猛威を振るう新型コロナウイルス感染症への対応でご苦労されている中で、多くの方々にご参加いただきまして有難うございます。
今回は、とっとり在宅ケア漢方クリニックの藤田先生と、ル・サンテリオン鹿野の三橋さんにお世話をいただき、片原ごとうクリニックの後藤先生を講師に迎えて、便秘をテーマに皆で考えようという企画をしていただきました。排便は多くの高齢者の方に共通した、関心の高い問題であります。また、排便を整えることにより、ショックといったトラブルの回避や、ADL改善にもつながる医療介護上の重要なテーマでもあると思います。最近は優れた薬も多く現れているようです。今日は久しぶりにグループワークも計画されており、日常の医療介護について改めて考えてみる、大切な機会となることと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。
◆ 演 題: みんなで考える 便秘💩のこと
◆ 講 師: 片原ごとうクリニック 院長 後藤 大輔 先生
◆ 世話人: とっとり在宅ケア・漢方クリニック 副院長 藤田 良介 先生
ル・サンテリオン鹿野 三橋 由希子 氏 (介護福祉士)
(三橋世話人より)
本日は、初めに後藤大輔先生にご講演いただき、その後、藤田先生より2事例をお話いただきグループワークを行います。よろしくお願いします。
【 概 要 】
在宅、介護の現場でも、お通じに関してのご苦労が多々あると思います。日常の現場でも、便秘は非常に難渋しますので、今回は便秘をテーマに皆さんと考えることができればと思い、お話をさせていただきます。
便秘の診断基準、便秘の種類と原因、便秘薬について、2017年に日本で定義されたガイドラインをベースに講演。また、便秘とトイレの関係についても解説。大事なこととして、適切な薬を使用する、排便形態を知る、生活改善とトイレの関わり、そして一番大事なことは、便秘と真摯に向き合うこと。
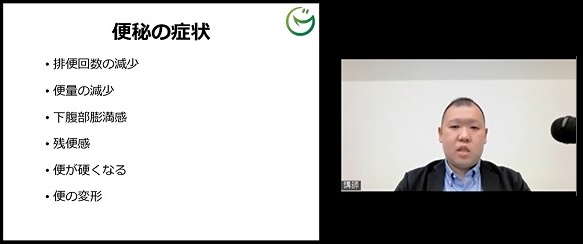
【 事 例 】
①80代女性、アルツハイマー型認知症。便秘のため下剤を使用しているが、排便状態はよくない。糞便性イレウスになったこともあり。デイサービス以外では常に寝ている。
▶ 便通コントロールのために出来ることは?
・本人の訴えがなければ、軟便でも出せる状態であれば良しとしている。
・ヘルパーさんに頼んで排便記録をつける。
・デイサービスで水分摂取を促す。
・介護士さんや家族による腹部マッサージ。
・リハビリの導入。
・処方薬の見直し。
②70代女性、夫と二人暮らし。下剤を飲まないと排便しないが、少量の下剤でも下痢や爆発的排便があり困っている。水分摂取を促すと頻尿となり、トイレが間に合わないこともある。
▶ 便通コントロールのために出来ることは?
・本人の訴えがなければ、軟便でも出せる状態であれば良しとしている。
・普段食事を作っている夫への助言(食事リズムや内容など)
・歩いたり腹筋など軽い運動を促す。
・一度精査してもらい原因を調べてもらう。
・栄養士の介入。
・刺激性下剤の中止し、漢方薬を増量。
・腹部マッサージと温罨法の提案。
それぞれの職種でできること…医師→処方薬の見直しやポリファーマシー対応、看護師→摘便、浣腸、下剤の調性、薬剤師→処方薬の見直し、排便状況の確認、リハビリ→日中の活動訓練、排便リハビリ指導、介護士→腹部マッサージや温罨法、排便誘導、栄養士→食事内容の確認、家族→腹部マッサージや温罨法、排便誘導 など、多職種で工夫しながら排便コントロールを行うことで、患者さんは快適に過ごすことができるのではないか。
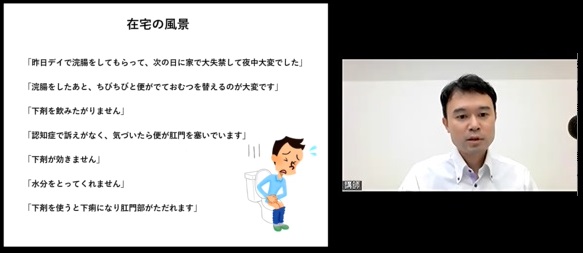

◆ 参加者:38名 ( 医師 12名、薬剤師 4名、看護師 5名、介護支援専門員 8名、事務職 3名
保健師・MSW・理学療法士・社会福祉士・介護福祉士、認知症地域支援相談員 各1名 )